FLAC モノラルファイルデータベース>>>Top
チャイコフスキー:交響曲第6番 ロ短調 作品74 「悲愴」
セルゲイ・クーセヴィツキー指揮 ボストン交響楽団 1946年2月9日録音をダウンロード
- Tchaikovsky:Symphony No.6 in B minor, Op.74 "Pathetique" [1.Adagio - Allegro non troppo]
- Tchaikovsky:Symphony No.6 in B minor, Op.74 "Pathetique" [2.Allegro con grazia]
- Tchaikovsky:Symphony No.6 in B minor, Op.74 "Pathetique" [3.Allegro molto vivace]
- Tchaikovsky:Symphony No.6 in B minor, Op.74 "Pathetique" [4.Adagio lamentoso]
私は旅行中に頭の中でこれを作曲しながら幾度となく泣いた。
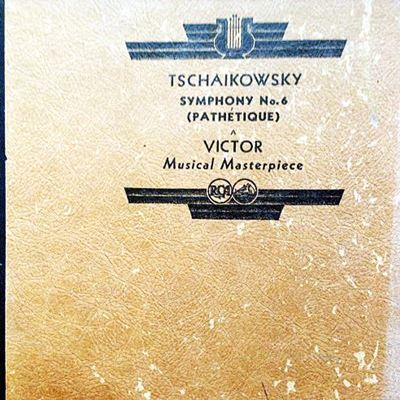
チャイコフスキーの後期の交響曲は全て「標題音楽」であって「絶対音楽」ではないとよく言われます。それは、根底に何らかの文学的なプログラムがあって、それに従って作曲されたというわけです。
もちろん、このプログラムに関してはチャイコフスキー自身もいろいろなところでふれていますし、4番のようにパトロンであるメック夫人に対して懇切丁寧にそれを解説しているものもあります。
しかし6番に関しては「プログラムはあることはあるが、公表することは希望しない」と語っています。弟のモデストも、この6番のプログラムに関する問い合わせに「彼はその秘密を墓場に持っていってしまった。」と語っていますから、あれこれの詮索は無意味なように思うのですが、いろんな人が想像をたくましくしてあれこれと語っています。
ただ、いつも思うのですが、何のプログラムも存在しない、純粋な音響の運動体でしかないような音楽などと言うのは存在するのでしょうか。いわゆる「前衛」という愚かな試みの中には存在するのでしょうが、私はああいう存在は「音楽」の名に値しないものだと信じています。人の心の琴線にふれてくるような、音楽としての最低限の資質を維持しているもののなかで、何のプログラムも存在しないと言うような作品は存在するのでしょうか。
例えば、ブラームスの交響曲をとりあげて、あれを「標題音楽」だと言う人はいないでしょう。では、あの作品は何のプログラムも存在しない純粋で絶対的な音響の運動体なのでしょうか?私は音楽を聞くことによって何らかのイメージや感情が呼び覚まされるのは、それらの作品の根底に潜むプログラムに触発されるからだと思うのですがいかがなものでしょうか。
もちろんここで言っているプログラムというのは「何らかの物語」があって、それを音でなぞっているというようなレベルの話ではありません。時々いますね。「ここは小川のせせらぎをあらわしているんですよ。次のところは田舎に着いたうれしい感情の表現ですね。」というお気楽モードの解説が・・・(^^;(R.シュトラウスの一連の交響詩みたいな、そういうレベルでの優れものはあることにはありますが。あれはあれで凄いです!!!)
私は、チャイコフスキーは創作にかかわって他の人よりは「正直」だっただけではないのかと思います。ただ、この6番のプログラムは極めて私小説的なものでした。それ故に彼は公表することを望まなかったのだと思います。
「今度の交響曲にはプログラムはあるが、それは謎であるべきもので、想像する人に任せよう。このプログラムは全く主観的なものだ。私は旅行中に頭の中でこれを作曲しながら幾度となく泣いた。」
チャイコフスキーのこの言葉に、「悲愴」のすべてが語られていると思います。
音楽に民主主義はいらない。
クーセヴィツキーのことを「素人」と貶したのはトスカニーニでした。
確かに、彼の音楽家としての出発点はコントラバス奏者であり、ピアノもまともに弾けなかったと言う話も伝えられています。指揮者を志したのはニキッシュの演奏に接して感激したからであり、スコア・リーディングに関しても全くの独学で身につけました。
こういう条件だといかに内面に優れた音楽性を持っていても指揮者として大成するのは難しいのですが、その困難を乗りこえる幸運を彼は持っていました。それは大富豪の娘を妻として得たことです。それはお金の心配をしないで音楽活動に専念できるというレベルのお金持ちではなく、自前でオーケストラを組織して指揮活動が出来たり、さらには自前の楽譜出版社を作って著名な作曲家に新作を次々と委嘱できると言うほどの「大富豪」だったのです。
そのおかげで、ラヴェル編曲の「展覧会の絵」から始まってバルトークの管弦楽のための協奏曲、メシアンのトゥーランガリラ交響曲、コープランドの交響曲第3番、オネゲルの交響曲第1番、プロコフィエフの交響曲第4番、ルーセルの交響曲第3番、ハンソンの交響曲第2番等など列挙するのも疲れるほどに重要な作品を後世に残してくれました。
そんなクーセヴィツキーですから、アメリカの名門オケであるボストン響の常任指揮者に就任しても「オレ流」を通したのは当然です。
クーセヴィツキーと言えば豪快な演奏が持ち味と言われるのですが、作品によっては結構振り幅が広くて、激情的な盛り上げを狙った入念な表情付けを行うことも少なくなかったようです。そして、作品や演奏の場によって音楽のスタイルが変わるあたりをトスカニーニは「素人」と断じたのでしょうが、それはかなり正当な評価だったと言えます。
しかしながら、そう言う気まぐれにつき合わされるオーケストラのメンバーは大変だろうと思われます。例えば、40年代のチャイコフスキーの4番から6番までの演奏を聞いてみると、豪快さよりは入念な表情付けの方に驚かされます。スコアなどはほとんど無視をしてテンポを動かし強弱のメリハリなどもつけたりしているのですから、そりゃあオケは大変です。
ところが、クーセヴィツキーはリハーサルでは一切妥協することなく、オケに対してもかなり居丈高で理不尽な言葉を発するのが常だったので、その関係は常に「最悪」だったと伝えられています。これが普通の指揮者なならば今後のことを考えればもう少し信頼感を築こうと努力するのですが、大富豪のクーセヴィツキーにしてみれば自分が気に入らなければいつでもやめてやるという姿勢で臨むことが出来たのです。
ですから、いかに厳しいリハーサルであっても常に筋が通っているトスカニーニなんかよりははるかにたちが悪かったと言えます。
ところが、困ってしまうのが、そう言う無茶を要求しながら、さらには素人くさい指揮であっても出来上がった音楽は魅力的なのです。それは、結局はクーセヴィツキーという男の中にすぐれた音楽が宿っていたからでしょうし、その事に彼自身も揺るぎない自信を持っていたはずです。
そして、こういう理不尽な仕打ちの上に成り立つ音楽は今後復活することは二度とありません。もしも、今の時代にクーセヴィツキーと同じような態度でリハーサルに臨めば、おそらく最初の1日でお払い箱となるでしょう。
そして、いつも思ってしまうのです。
音楽に民主主義はいらない。