FLAC モノラルファイルデータベース>>>Top
シューベルト:劇付随音楽 「ロザムンデ」D797(抜粋)
ハンス・シュミット=イッセルシュテット指揮 北ドイツ放送交響楽団 1955年12月7日~15日録音をダウンロード
- Schubert:Rosamunde, Iincidental Music, D 797 [1.Entr'acte, No.1]
- Schubert:Rosamunde, Iincidental Music, D 797 [3.Ballet, No.1]
- Schubert:Rosamunde, Iincidental Music, D 797 [3.Ballet, No.2]
- Schubert:Rosamunde, Iincidental Music, D 797 [4.Entr'acte, No.2]
音楽だけは残った(^^v
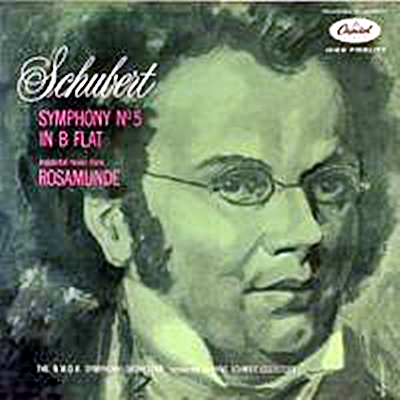
ロザムンデと言えばシューベルトと結びつくほどにこの作品は有名です。
原作は、ベルリン出身の女流作家ヘルミーネ・フォン・シェジーの戯曲「キプロスの女王ロザムンデ」です。しかし、この戯曲はおそろしく出来の悪いもので、わずか2日で上演が打ち切られてしまいました。
しかし、幸いだったのは、この戯曲に付随音楽をつけたのがシューベルトだったことです。
おかげで、戯曲の方は台本も残らないほどのお粗末さだったのに、このシューベルトの音楽によって女流作家ヘルミーネ・フォン・シェジーの名前は歴史に刻まれることになりました。
なお、この劇音楽の序曲は今日では「ロザムンデ序曲」と呼ばれているのですが、実は別の作品のための序曲だったものを使い回したものでした。しかし、本来の出所であるオペラ「アルフォンゾとエストレラ」はほとんど忘却の彼方に行ってしまったために、本来は「アルフォンゾとエストレラ」序曲とよぶべきはずのものが「ロザムンデ序曲」として定着してしまいました。
しかし、この美しいメロディはシューベルトが書いた音楽の中でも屈指のもので、その美しさと「ロザムンデ」のイメージとあまりにも見事に結びついているが故に、やはりこれは「ロザムンデ序曲」とよぶしかないと思えます。
全曲は上記の序曲と10曲からなりますが、一般的には序曲と第3幕間奏曲、そしてバレエ音楽第1番・第2番が抜粋して演奏されることが多いようです。とりわけ、第3幕間奏曲は弦楽四重奏曲第13番「ロザムンデ」に転用されているのでとりわけ有名です。
- 「序曲」
- 「間奏曲第1番」
- 「バレエ音楽 第1番」:木管楽器の響きが素晴らしい!!
- 「間奏曲 第2番」
- 「ロマンス<満月は輝き>」:アルトの独唱です。
- 「亡霊の合唱<深みの中に光が>」:男声合唱です。
- 「間奏曲 第三番」:弦楽四重奏曲第13番の第2楽章に登場する有名なメロディです。
- 「羊飼いのメロディ」
- 「羊飼いの合唱<この草原で>」:混声合唱です。
- 「狩人の合唱<緑の明るい野山に>」:混声合唱・男声合唱・女声合唱で歌われます。
- 「バレエ音楽 第二番」:終曲です。
「Capitol」録音で窺えるイッセルシュテットの新しい顔
イッセルシュテットの録音を調べてみると、それが実に様々なレーベルからリリースされていることに驚かされます。ざっと数え上げるだけで「Telefunken」「Decca」「Capitol」「Melodiya」「Mercury」等々です。
言うまでもないことですが、昔は演奏家とレコード会社の「契約」は絶対的なものでしたから、気楽にその「契約」の枠を超えて録音を行うことは出来ませんでした。
ですから、いろいろなレーベルで録音を行っているというのは、あちこちから引っ張りだこというわけではなくて、腰を据えて録音活動を行えるような契約が結べていなかったことを意味しているのです。
たとえば、50年代初期の「Decca」との録音を振り返ってみても小品の録音が大半を占めていて、その扱いの悪さは明らかです。
そう言う意味では、「Capitol」がヨーロッパでのクラシック音楽の録音に取り組み始めた矢先に「EMI」に吸収されたのは、イッセルシュテットにしては不幸な出来事でした。
何故ならば、「Capitol」はレーベルのレパートリーを作りあげていく上での軸となる指揮者としてイッセルシュテットを起用するつもりだったからです。それは、イッセルシュテットにとっては願ってもないチャンスでもありました。
そう言う意味では1955年の4月と12月に集中的に行われた「Capitol」との録音には強い意気込みをもって臨んだものと思われます。そして、そう言うレベルの録音がこの後も継続的に続けられていれば、イッセルシュテットという人の評価も大きく変わっていたかもしれません。
しかし、その「Capitol」が「EMI」に吸収合併されることで、両者の関係はその2度で終わってしまいました。
その後の録音歴を見てみると、様々なマイナーレーベルでも録音を行っているのですが、50年代の後半にバックハウスの伴奏(ベートーベンのピアノ協奏曲全集)という形で「Decca」と録音し、60年代の後半には同じく「Decca」でべー十ーベンの交響曲全集を録音しています。
ですから、彼の録音歴の背骨らしきものは「Decca」が担っていると言えるのでしょうが、「Decca」の側の彼に対する評価はなかなか定まらなかったようです。
そして、改めてこの「Decca」での初期の録音を聞き直してみて気づくのは、その演奏スタイルの「古さ」です。
おかしな話ですが、今という時代からこういう演奏を聞けばその「古さ」が逆に好ましく思えたりするのですが、これを50年代の初め頃においてみれば、それはひたすら「古かった」はずです。
そう言えば、この時代の北ドイツ放送交響楽団のコンサート・マスターはエーリヒ・レーンで、チェロのトップはアルトゥール・トレースターだったはずです。この二人は戦前のベルリンフィルでも同じポジションにいたプレーヤーです。
戦後、フルトヴェングラーがこのオケにたびたび客演指揮をしたのはそういう事情もあった為だと言われています。
この、良く言えば馥郁とした、悪く言えばボッテリとした響きは、同じ時代に日の出の勢いで登場してきたカラヤン&フィルハーモニア管の響きと較べてみれば明らかに過去のものであり、「Decca」にしても彼らの核を成すアンセルメ&スイス・ロマンド管の響きとも異質なものでした。
しかし、そう言うスタイルをイッセルシュテットは最後まで変えることはなかったようです。そこには、ドイツ音楽の復興を託されたという自負があったからでしょう。
そんなイッセルシュテットがこの世を去ってから40年以上の時が経て、その時の流れの中でクラシック音楽も様々なムーブメントに翻弄されてもみくちゃにされてきました。
そして、そのもみくちゃにされた果てから過去を振り返ってみれば、こういう古さに懐かしさと大いなる価値を見いだす人もいるのかもしれません。
しかし、「Capitol」との録音には熱気がみなぎっています。ここで紹介しているロザムンデなども驚くほどの推進力と熱気に満ちていて、そう言う古さから脱却しようとしてるような雰囲気も感じさせられます。
結果として、「Capitol」との関係が思わぬ事で無に帰したことで、古き良きイッセルシュテットが残ったとも言えます。後の気楽な世代からすれば、それはそれで良きことだと言えるのですが、イッセルシュテットにしてみれば無念やるかたなしだったことでしょう。