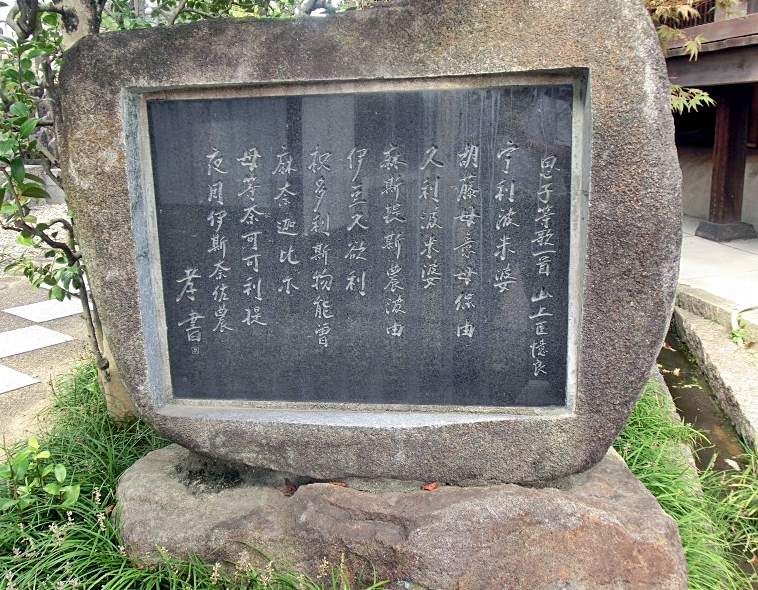万葉文化館の8月の講座は「巻5の801~802」の「子らを思(しの)へる歌」でした。講師は吉原啓先生でした。
「子らを思(しの)へる歌 一首あわせて序」となっていますから「序文」と「長歌」、そして「反歌一首」から成り立っています。
そして、その反歌は万葉集のなかでももっとも有名なものの一つで、おそらく誰もがどこかで一度は目にしたことがあるものです。
銀(しろかね)も金(くがね)も玉も何せむに勝(まさ)れる宝子に及(し)かめやも
そして、これに先立つ長歌も短いもので内容的にもそれほど難しいものではないので、これで1時間30分の講座が持つのかと危惧したのですが、持つんですね。(^^;
今回もまたなかなかに面白くもあり、興味深い内容の講座でした。
まずは、「序」から見ていきます。
釈迦如来の、金口(こんく)に正に説(と)きたまはく
「等しく衆生を思ふことは、羅候羅(らごら)の如し」と。
又説きたまはく「愛(うつくし)びは子に過ぎたるは無し」と。
至極(しごく)の大聖(たいしやう)すら、尚ほ子を愛(うつくし)ぶる心ます。
況むや世間(よのなか)の蒼生(あをひとくさ)の、誰かは子を愛(うつくし)びざらめや。
「金口」とは「尊い口」という意味です。
釈迦如来は全身が金色に輝いているので、その口もまた金色であり、その口から説かれる言葉もまた尊いのです。
では、その「金口」から何が説かれているのかと言えば、憶良は以下の二つを引用しています。
等しく衆生を思ふことは、羅候羅の如し
愛びは子に過ぎたるは無し
まず最初の言葉における「羅候羅」が分からないです。
「らごら」と読むようなのですが、まるで円谷プロの怪獣映画に出てきそうな名前です、・・・「怪獣ラゴラ」・・・。
もっとも、ここで怪獣ラゴラが暴れるわけはないのであって、「羅候羅」とはお釈迦様の子供の名前なのです。そう、釈迦が出家するときに「脱ぎ捨てた履物のように棄てた」と言われるあの子供のことです。
そして、この言葉は色々な教典の中にも出てくる言葉のようで、例えば「大般涅槃経巻第一寿命品第一の一」の中に「等しく衆生を観(み)たまふ事羅候羅の如し」という言葉があるようで、それは教典の中では釈迦自身の言葉とされています。
ただし、教典では「観たまふ」となっているものが、憶良の「序」では「思ふこと」となっているのは、おそらくは憶良による改変だろうと考えられています。
しかしながら、そう言い換えても全体の意味するところが大きく変わるわけではありません。
釈迦が衆生を見守り思いを致すのは、我が子である羅候羅を見守り思いを致すのと同じであると言うのです。
問題はその次の「愛びは子に過ぎたるは無し」の方にあります。
この言葉の出典は「雑阿含経巻三十六」の中に出てくる「愛するところは子に過ぐる無く」だと考えられています。
しかしながら、この教典をしっかり読むとこうなっているのです。
所愛無過子(愛するところは子に過ぐる無く)
財無貴於牛(財は牛より貴きは無く)
光明無過日(光明は日より過ぐる無く)
薩羅無過海(薩羅は海よりも過ぐる無し)
このように天子が言ったあとに、世尊はどのようにお考えですかと問いかけると釈迦はこう答えたというのです。
愛無過於己(愛するところは己れに過ぐる無く)
財無過於穀(財は穀に過ぐる無く)
光明無過慧(光明は慧に過ぐる無く)
薩羅無過見(薩羅は見に過ぐる無し)
つまりは、「愛するところは子に過ぐる無く」と言う言葉は明らかに天子の言であり、それを釈迦の言葉としてここで引用するのは明らかに誤りなのです。
そして、仏教の教義からいっても、「愛」という言葉が肯定的な意味を持って釈迦の口から説かれる事はないのです。
何故ならば、「愛」というのは「執着」を引き起こすものであり、それ故に「煩悩」の一つと考えられているからです。
ですから、一切の煩悩から自由となって解脱した存在である釈迦の口から煩悩の一つである「愛」が肯定的に語られるはずはないのです。
仏教ではその様な「執着」を生まずに他のものを思いやるものとしては「慈悲」という言葉が使われます。
つまりは、「等しく衆生を思ふことは、羅候羅の如し」という言葉の後に「また説きたまはく」として「愛びは子に過ぎたるは無しと続けるのは明らかに誤りなのです。
しかしながら、仏典に対しても漢籍に対しても深い教養を持っていた憶良がその様な単純なミステイクを犯すとは考えにくいのです。
じつは、これと似たような「ミステイク」というか「改変」は日本挽歌の「前置漢文」にも見られます。
憶良は、あの漢文の中で「釋迦能仁(しゃかのうにん)は、雙林(そうりん)に坐して、泥洹(ないをん)の苦(くるしみ)を免(まぬが)るること無し。」と述べています。
つまりは「釈迦であっても涅槃の苦しみからは逃れられなかった」と述べているのですが、これもまた一切の煩悩から自由となって解脱した存在である釈迦に対しては許されない解釈なのです。
ですから、それらの「誤り」は憶良の理解不足による「ミステイク」ではなくて、何らかの意図にもとづいた「改変」だと考えた方がしっくりくるのです。
それでは、その意図とは何かと推測すれば、その様な「改変」を行うことによって「至極の大聖すら、尚ほ子を愛ぶる心ます」と言う言葉を引き出すことを可能にし、その事によって「我が子への愛情の絶対性」を確保するためではないかと思われるのです。
そして、一種の三段論法として、釈迦でさえそれほどまでにわが子を愛したのだから「況むや世間の蒼生の、誰かは子を愛びざらめや。」という最終結論を導き出すのです。
では、何故にそこまでして我が子への愛を絶対化したかったのかと言えば、それはこの「子らを思へる歌」が「嘉摩郡三部作」の2番目の歌として、つまりは「惑へる情を反さしむるの歌」に続く歌として位置づけられていることを見ておく必要があるのです。
言うまでもなく「惑へる情を反さしむるの歌」とは、自ら倍俗先生と称して「妻子(めこ)を顧みずして、脱履(だつしつ)よりも軽(かろ)みす」する存在への反省をうながす歌でした。
そして、そこで憶良はあれこれと教え諭したものの、それでは不十分だとして、さらにもう一押しして、「我が子への愛の絶対化」を図ったのが「子らを思へる歌」だったと考えれば、その様な意図的改変の狙いがはっきりと見えてくるのです。
つまりは、そこで釈迦の存在を持ち出し、意図的にミステイクを犯し、あるいはミスリードをしてでも「我が子への愛」を絶対化させる必要があったのです。
そう考えれば、この歌は単純に。そして素直に我が子への愛を歌い上げただけではないこともまた浮かび上がってくるのです。(続く)