小川洋子の「沈黙博物館」を読んでいて、私がやっていることも「博物館作り」のようなものだと「自覚」させられました。
それにしても、これは不思議な物語です。
主人公は「博物館技師」である「僕」であり、物語はこの「僕」による一人称で語られていきます。「博物館技師」とは聞きなれない言葉なのですが、彼の言葉によると、新しい博物館を作るための一切の仕事を引き受けるようですから、いわゆる「学芸員」とも異なるようです。
彼は、博物館を作りたいという依頼があると現地におもむいて、博物館の器となる建物の設計から、収集物の整理・分類、そして陳列に至までのあらゆる仕事を一切引き受ける存在のようなのです。そして、僕は自らの仕事について次のように語ります。
「僕の仕事は世界の縁から滑り落ちたものをいかに多くすくい上げるか、そしてその物たちが醸し出す不調和に対し、いかに意義深い価値を見いだすことが出来るかに係っているんです。」
そんな僕を招いたのは不思議な老婆でした。
依頼主はひどく小柄だった。・・・小柄という言葉を突き抜けた、極限の小ささを体現していると言ってもよかった。その体格のためか、趣味の問題か、着ている洋服はどう評価していいのか見当もつかない代物だった。・・・まるで、彼女自身が、ソファーに着いた染みの一つみたいだった」
そして、変わっているのは外観だけでなく、どんなことがあっても他者とはなじもうとしない偏屈の塊のような人物でもあったのです。
長年老婆に仕えてきた庭師は「あの人に好かれようと思う方が無茶だよ」と語り、老婆のただ一人の身内である娘は「母は怒ってなどいないわ。あれは初対面の人に対する、母特有のはにかみみたいなもので、ごく普通の感情表現よ」というのです。
そして、物語は僕と老婆と、その娘である少女の3人が中心となって「形見の博物館」を作ることを縦軸としてすすめられていくのです。
老婆は、その村で亡くなった人の形見を、合法、非合法にかかわらず、あらゆる手段で集めていて、その膨大な「形見の品」をおさめた博物館作りを計画していたのです。
老婆の述懐によれば、そのような形見の収集は彼女が11才の時から始められたのですが、それは多くの困難を伴うものでした。
「困難の一番の原因は、いい加減な形見では満足しなかったという点である。・・・私が求めたのは、その肉体が間違いなく存在しておったという証拠を、もっとも生々しく、もっとも忠実に記憶する品なのだ。・・・思い出などと言うおセンチな感情とは無関係、もちろん金銭的価値など論外じゃ。」
そして、そこに「沈黙の伝道師」や「シロイワバイソン」「庭師が作るナイフ」「兄から譲り受けた顕微鏡」「母の形見であるアンネの日記」などが物語にふくらみを与えていきます。
しかし、とある殺人事件をきっかけに僕はこの村から逃げだそうとして駅に向かうのですが、そこでは時刻表は色あせ数字は消えていて、さらにはいつまで経っても汽車は来ないというあたりから、物語の風景は一変してしまいます。
それは、「いつまで経っても汽車は来ない」という現実によって、今まで疑う余地もなかった「死者」と「生者」の分別が急に曖昧になってしまうのです。
誰が「死者」であり、誰が「生者」であるのかが次第におぼろげになり、もしかしたら僕自身がすでに「死者」ではないのかという気がしてくるのです。
さらに言えば、僕が老婆とともに博物館を作ろうとしている村も「死者の村」ではないのかという気がしてきますし、沈黙の伝道師が「沈黙の業」に入るのは死を受け入れたと言うことではないのかという気がしてくるのです。しかし、物語はそのような疑問に対する明確な回答を与えないまま老婆の死を持って無限に続くと思われた形見の収集に終わりが来て幕を閉じます。
「あなたが収集した形見は、これで全部、すべてです。」
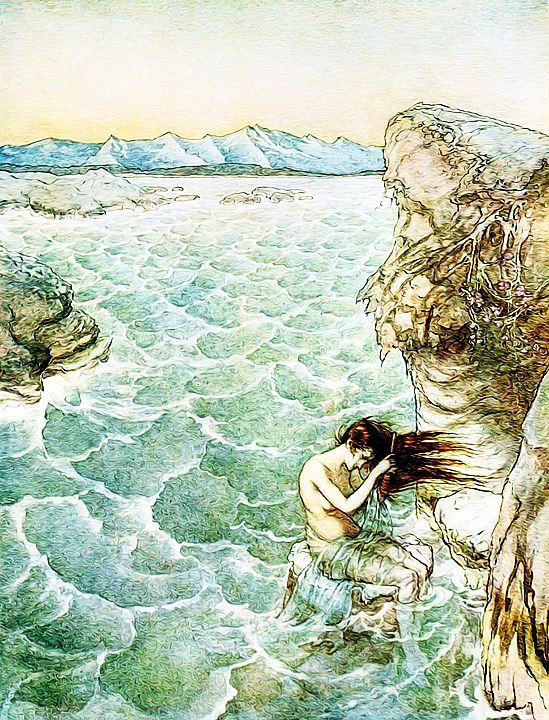 小川洋子らしい静謐で透明感に溢れた物語であり、読み終えた後にある種の欠落感を感じさせられるのも小川洋子の特長でしょう。そして、その欠落感ゆえに、時をおいて再読したくなる物語でもあります。
小川洋子らしい静謐で透明感に溢れた物語であり、読み終えた後にある種の欠落感を感じさせられるのも小川洋子の特長でしょう。そして、その欠落感ゆえに、時をおいて再読したくなる物語でもあります。
しかし、私にとっては、それ以上にここで展開される「博物館」をめぐって語られる言葉の方が深く印象に残ったのです。
「ものを保存しておくって、考えていたよりずっとややこしいことね。」
「当たり前さ。大抵の物は、放っておけばただのボロボロした粉になってしまう。・・・みんな世界を分解したがっている。不変でいられるものなんて、この世にはないんだ。」
そして、僕は膨大な収蔵品の燻蒸を行い、一点一点を資料カードに記していきます。そうすると、最初はよそよそしかった収蔵品が次第に親愛の情を醸し出すようになり、収蔵品が持つ時間と記憶が巧妙に組み合わさって統一されたある空気を生み出すようになっていくのです。
しかし、圧巻なのは、その一点一点の形見に対して行われた僕と老婆による「文書化作業」です。
老婆の前に一点の形見を置くと、少し考え込んだ老婆はやがてその形見にまつわる物語を語り出します。そして、その語りを僕は書き記していくのです。
その物語は気まぐれな老婆の気性を考えれば大変な困難を伴う作業になるものと思われたのですが、実際は驚くべきものでした。
「いったん口を開くと、毛糸玉を一つ解くように、言葉が滑らかに紡ぎ出された。途中で糸が切れたり、絡まったりすることはなく、最初と最後がちゃんと一続きになっていた。しかも、その毛糸玉に、僕が求める情報は全部含まれていたし、余分なものは一つも混じっていないのだった。」
「僕が鉛筆を置いた段階で、すでにノートには完全な背景資料が出来上がっていた。文脈の乱れも、矛盾も言い間違いもなかった。それは老婆の記憶に刻み込まれた、形見をめぐる一つの物語だった。」
そして、僕は老婆の驚くべき記憶力に驚嘆するのですが、それが大きな誤りでったことが最後に明らかとなります。
「僕が収集した形見の文書化については、どうしたらいいんでしょう。」
「質問の意味が分からん。」
「つまり、僕が村に来てから収集された、ごく最近の形見については、誰が語ることになるのでしょうか。」
「お前じゃ。」
その老婆の言葉に驚いた僕は次のように疑問を投げかけます。
「でも僕は形見の持ち主と話したこともなければ、顔さえも知らないんですよ。語るべき情報なんて、何一つ持っていません。」
「私が喋っているのがたんなる情報だと思われていたとは、ああ情けない。何のために毎日毎日、喉をからし、端を詰まらせてきたのか。お前と共有した時間のすべてを、どぶに捨てられた気分じゃ。」
「すみません。謝ります。僕が本当に言いたかったことは、全く逆です。形見について真実を語る資格があるのは、あなただけではないか、ということなんです。」
「形見について語れるのは、それを収集した人間のみである。持ち主のことを知っていようがいまいが、関係ない。然るべき時が来れば、お前もまた語るようになる。」
パブリック・ドメインという「音楽の形見」を前にして、語るべき事を語れているのか、自戒しなければいけません。