シェーンベルクの作品の中では最も親しまれている音楽
ある方が、シェーンベルクの無調の作品のことを「音楽史的には革命的な業績として評価はされるけれども、昔も聞かれなかったし、今も聞かれることはなく、そしてこれからも聞かれることはない」音楽だと紹介していました。
実にもって上手い言い回しだなとは思いつつも、しかし、個人的には彼の無調の作品は聞いてきたし、できれば一人でも多くの人に聞いてほしい音楽だとは思っているので、何となく残念な思いがしたものです。
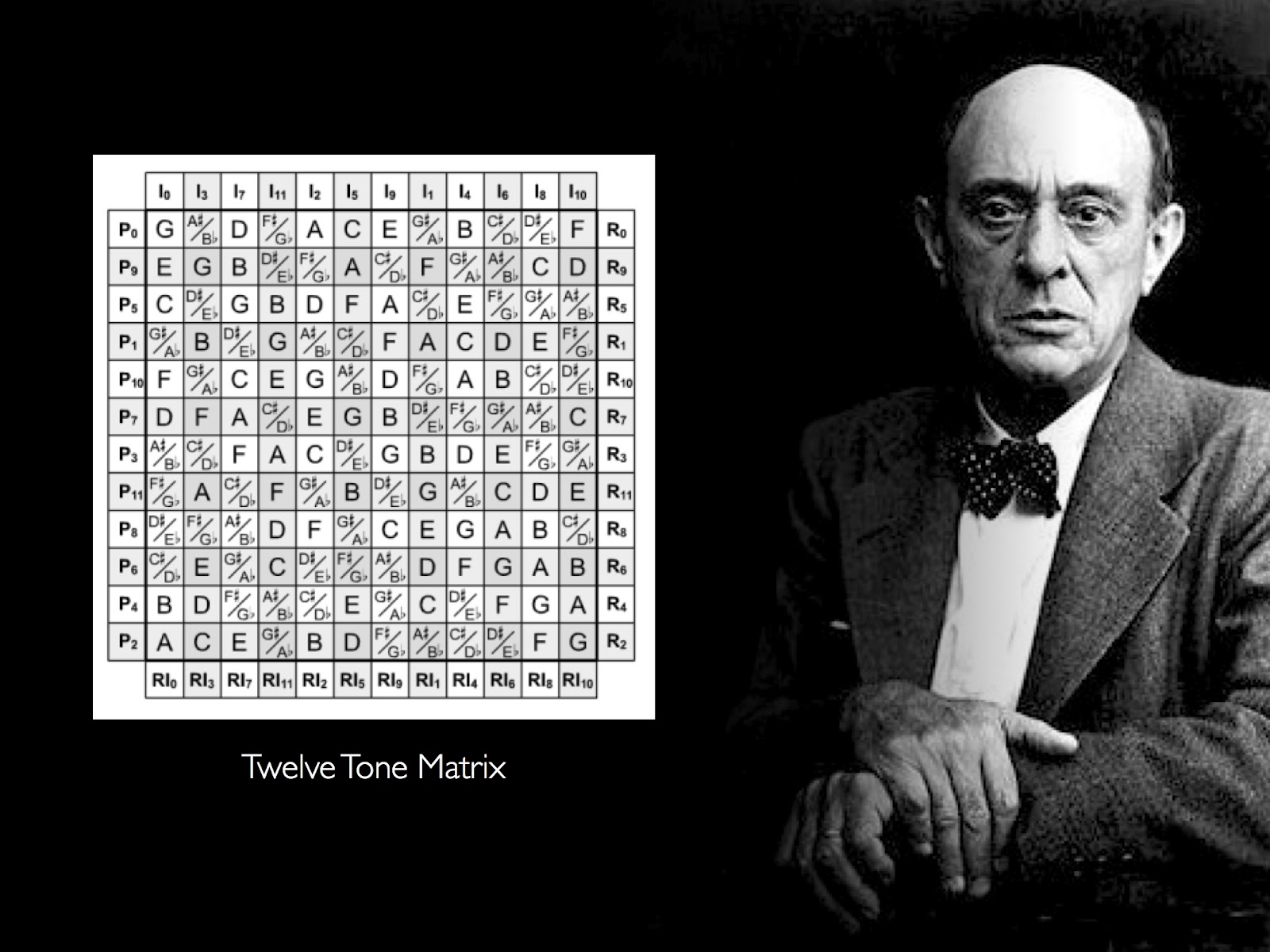
Arnold Schönberg
シェーンベルグやウェーベルン、ベルクなどに代表される音楽は、一見すると、戦後のクラシック音楽界を席巻した「前衛音楽」につながっていくように見えながら、その本質において全く異なるものだと思っています。
その違いはひと言で言えば、人の心に響く「何か」があるか否かです。
確かに、彼の「弦楽四重奏曲」や「月に憑かれたピエロ」が広く聞かれるようになるとは思いませんが、しかし、戦後のあの「前衛音楽」などとごっちゃまぜにされるのは根本的に間違っていると思いますので、何とか音源を探し出してきて紹介していきたいと思います。
とは言え、結果としては、シェーンベルグは「グレの歌」やこの「浄められた夜」だけが長く聞かれ続けるのかもしれません。
そう言えば、ピカソにしても、若い頃の「青の時代」の絵が本当はみんな大好きなんです。
佇まいは、両者とも同じかもしれません。
この、当初は弦楽六重奏曲の作品として書かれ、その後好評に応えて弦楽合奏にも編曲されたこの作品は、系譜としては紛う事なき後期ロマン派の音楽です。
確かに、ワーグナーからの強い影響のもとに作曲されたので、トリスタン的な調性の定まらない音楽になっています。
しかし、いわゆる無調音楽の不安感は全くなくて、逆に何とも言えない浮遊感を生み出しています。そして、その浮遊感が、このエロティックな詩に見事なまでにマッチングしていて、見事な限りです。
なお、シェーンベルグに霊感を与えたデーメルの詩は、今となっては安っぽい昼メロの域を出るものではないように思いますが、作品が発表された19世紀末においてみればかなりインパクトのあったテーマだったのでしょう。
しかしながら、それにつけられたシェーンベルグの音楽は掛け値なしに素晴らしいので、おそらくはそのおかげで、デーメルの名も長く残ることになるでしょう。
それは、シューベルトの「冬の旅」におけるヴィルヘルム・ミュラーと同じ立ち位置かもしれません。
「浄められた夜」 リヒャルト・デーメル(訳:喜多尾道冬)
男と女が寒々とした裸の林のなかを歩んでいる、
月がその歩みに付き添い、ふたりを見おろしている。
月は高いかしの木の梢の上にかかっている、
空は澄み渡り、一片の雲もなく、
黒い木の梢が空にのこぎりの歯のように突き刺さっている。
女がひとり語りはじめる。
わたしは身ごもっています、でもあなたの子ではありません。
わたしは罪に苦しみながらあなたと歩んでいるのです。
わたしはひどい過ちを犯してしまったのです。
もう幸せになれるなどと思いもしませんでした、
それなのにどうしても思いを断てなかったのです、
子供を生むこと、母となるよろこびとその義務を。
それで思い切って身を委ねてしまったのです。
おぞましい思いをしながらも女としての性(サガ)を、
心も通わぬ男のなすがままにさせてしまったのです、
それでも満ち足りた思いをしたのでした。
ところが人生は何という復讐をするのでしょう、
わたしはあなたと、ああ、あなたと出会ったのです。
女はとぼとぼと歩んでゆく、
女は空を見上げる、月がともについてくる、
彼女の暗い瞳が月の光でいっぱいに満ちる、
男がひとり語りはじめる。
きみの身ごもっている子供を
きみの心の重荷とは思わぬように。
ほら見てごらん、あたりはなんと明るくかがやいていることか!
このかがやきは森羅万象にくまなくおよんでいる、
きみはぼくと冷たい海の上を渡っている、
でもその底ではあたたかさが交流している、
きみからぼくへ、ぼくからきみへと。
このあたたかさがお腹の子を変容させるだろう、
きみはその子をぼくの子として産んでほしい、
きみはこのかがやきでぼくを変容させてくれた、
きみはぼくそのものを子供にしたのだ。
男は女の厚い腰を抱いた、
ふたりの息はあたたかくまじり合った。
男と女は明るく高い夜空のなかを歩んでゆく。
デーメルの詩は上のように5つの部分で分かれているのでシェーンベルグの音楽もそれに対応してきちんと5つの部分に分かれています。
しかし、連続して演奏されるので通常は単一楽章の音楽と見なされます。

Leopold Stokowski
シェーンベルク:浄められた夜 作品4 ストコフスキー指揮 ストコフスキー・シンフォニー・オーケストラ 1957年8月録音
 そんなシェーンベルグの後期ロマン派風の音楽を「これぞ昼メロ!!」という感じで再現してみせたのがストコフスキーでした。
そんなシェーンベルグの後期ロマン派風の音楽を「これぞ昼メロ!!」という感じで再現してみせたのがストコフスキーでした。
いかに後期ロマン派の範疇に入る音楽だとはいえ、わけの分からない「無調音楽の大家」というレッテルの貼られたシェーンベルグの音楽をこの時代に取り上げたストコフスキーはやっぱりエライと思います。
ですから、この録音を聞いて、縦の線が不明瞭だとか、アンサンブルが緩いとか、オケの響きに脂肪分が多すぎるなどと文句を言ってはいけません。(^^;
50年代後半に舞い戻ってみてください。
レコード屋さんに言って手に取ったLPのジャケットに「シェーンベルグ作曲 浄められた夜 作品4」と書いてあるだけで、ほとんどの人は引いてしまいます。
しかし、そこでかろうじて踏みとどまった人は、「レオポルド・ストコフスキー指揮」というクレジットを目にとめて、「もしかしたら、これなら面白く聞けるかもしれない」と思い直して買ってくれるのです。
ですから、針を落として流れてきた音楽が「これぞ昼メロ!」(そんな時代に昼メロはないか^^;)と思えるような、ドロドロの愛憎劇を演じてくれると、「ああ、やっぱり買ってきてよかった」と思ってくれるのです。
おかしな言い方かもしれませんが、この1950年代という時代において、録音という行為の意義と本質を本当に理解していたのはストコフスキーとカラヤンだけだったと思います。
ただ、ストコフスキーファンの方には不本意な言い方かもしれませんが、少しだけカラヤンの方が「芸術の香り」が高かったので、結局は彼が「帝王」となれたのです。
でも、そのおかげで、「面白ければ何でもあり」という路線をストコフスキーは突っ走ってくれたので、それはそれで有り難い話ではあったのです。