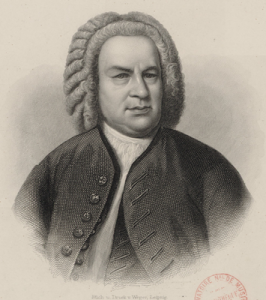歴史の証言者としての音楽
音楽を語るのに、音楽以外のあれこれを持ち出して論議するのを嫌う人がいます。私自身も基本的にはそういうスタンスを取っていますが、それでも、時にはそういう「あれこれ」にふれずにはおれない演奏というものがあります。
このメンゲルベルグ指揮のあまりにも有名な「マタイ受難曲」も、その、「ふれずにはおれない演奏」の一つです。
バッハ:マタイ受難曲
今の趨勢から見れば「論外」と切って捨てる人もいます。
まずもって、大編成のオーケストラと合唱団を使った演奏スタイルが許せないと言う人もいるでしょう。
至るところに見られるカットも我慢できないと言う人もいるでしょう。
解釈に関わる問題でも勘違いと間違いだらけだと憤慨する人もいるかもしれません。例えば、フェルマータの処理をそのままフェルマータとして処理している、等々。今ではバッハのフェルマータは息継ぎの指示程度にしか受け止められていません。
しかし、どのような批判をあびたとしても、やはりこの演奏は素晴らしく、20世紀の演奏史における一つの金字塔であることは確かです。
この演奏の数ヶ月後、ナチスドイツはポーランド国境になだれ込んで第2時世界大戦が始まりました。一年後には、中立国だから戦争とは無縁だとの幻想にしがみついていたオランダ自身もまた、ナチスに蹂躙される運命をむかえます。
メンゲルベルグによるこの演奏会は、その様な戦争前夜の緊張感と焦燥感のもとで行われたものでした。
当時のオランダのおかれた立場は微妙なものでした。
侵略の意図を隠そうともしないナチスドイツの振る舞いを前にして、自らの悲劇的な行き末に大きな不安を感じつつも、日々の生活では中立的な立場ゆえに戦争とは無縁だという幻想にしがみついて暮らしていたのです。
悲劇というものは、それがおこってしまえば、道は二つしかありません。
踏みつぶされるか、抵抗するかであり、選択肢が明確になるがゆえにとらえどころのない焦燥感にさいなまれると言うことは少なくなります。
しんどいのは、悲劇の手前です。
人間というものは、その悲劇的な未来が避け得ないものだと腹をくくりながらも、あれこれの要因をあげつらってはあるはずのない奇跡に望みを託します。この、「もしかしたら、悲劇を回避できるかもしれない」という思いが抑えようのない焦燥感を生み出し、人の心を病み疲れさせます。
この演奏会に足を運んだ人たちは、その様な「病みつかれた」人たちでした。
そして、疑いもなく、自らを受難に向かうキリストに、もしくはそのキリストを裏切ったペテロになぞらえていたことでしょう。
冒頭の暗さと重さは尋常ではありません。最後のフーガの合唱へとなだれ込んでいく部分の激烈な表現は一度聴けば絶対に忘れることのできないものです。
そして、何よりも、マタイ受難曲第47曲「憐れみたまえ、わが神よ」!!
独奏ヴァイオリンのメロディにのってアルトが「憐れみたまえわが神よ、したたりおつるわが涙のゆえに!」と歌い出すと、会場のあちこちからすすり泣く声が聞こえてきます。
ポルタメントを多用してこの悲劇を濃厚に歌いあげるヴァイオリンの素晴らしさは、今の時代には決して聴くことのできないものです。
まさに、この演奏は第2時世界大戦前という時代の証言者です。
ちなみに、この4年後、1943年にローゼンストックによる指揮でマタイ受難曲が東京で演奏されています。記録によると、その時も会場のあちこちからすすり泣きの声が聞こえたと言われています。
逆から見れば、バッハのマタイは時代を証言するだけの力を持っていると言うことです。
<2015年3月8日追記>
ノンフィクション作家として有名な柳田邦夫は、この演奏に関わって傾聴に値するいくつかのエッセイを書かれています。「かけがえのない日々」「犠牲(サクリファイス)」などなど・・・。
その中で、ピリオド演奏を標榜する一部の人たちがこのメンゲルベルグの演奏を酷評し、それだけでは飽きたらず、この演奏を聞いて感動する多くの人々を冷笑していることを厳しく批判しています。さらに柳田は、そう言う批判をする人の代表として磯山雅氏の名をあげていますから、その批判は決して無責任な一般論ではありません。
柳田の一文は、そのようなイデオロギーによって押し進められているピリオド演奏という潮流が、いかに音楽の本質から外れたものかを鋭くついています。
興味があれば一読をおすすめします。
「マタイ受難曲」とは、どのような音楽なのか。
普通に演奏して、約3時間半という大曲です。
「来たれ、娘たちよ、我とともに、嘆け」とホ短調で壮大に歌いだされる冒頭合唱から、「我ら涙流しつつひざまずき、御墓なる汝の上に願いまつる」と締めくくられる終末合唱まで、まさに一分の隙も緩みもなく展開される音楽ドラマ、それがマタイ受難曲です。
しかし、全曲が強い緊張感で維持されているといっても、そこはドラマ故にいくつかの起伏があります。そして、この音楽の最大の山場は、第46曲を中心としたその前後の「ペテロの否認」の場面だと考えます。
実は、この場面の重要性を教えてくれたのは、遠藤周作の「キリストの誕生」と「沈黙」でした。
キリストの受難物語というのは日本人にとってなじみのあるテーマではありません。
欧米の人々にとっては常識的に理解できることでも、この分野のことになると日本人にとっては理解困難なことが多いといわざるを得ません。実際、遠藤の著作を通して多くのことを教えられてからは、この受難物語のテキストの意味するところを全く理解ししないで、見当違いなことをいっている評論家の多いことには驚かされました。
弟子達の視点から受難物語を見ると
遠藤は、この受難物語で最も興味を引かれるのは、キリストの受難そのものではなく、「キリストの受難」という衝撃的な事実に遭遇した「駄目人間」の集まりである、彼の弟子グループの生き様にあることを何度も語っています。
何故、キリストの受難に際して、人間の弱さと駄目さをさらけ出した弟子グループが、それ以後どうして信仰を守り続けることができたのか、何故に激しい弾圧の中で命を落としてまでも信仰を守り続けるほどの「強い人」に変わり得たのか、その疑問を遠藤は何度も何度も繰り返しています。
そして、結論として遠藤は、キリストその人の中にそのような駄目人間に力と勇気を与えた何者かがあったことを語っています。遠藤は、その何者かを「X」と語っていますが、その「X」が多くの人々の人生に決定的な何かを与え、その人の人生を大きく変えたことを熱く語っています。
そのイエスの持つ「X」が集約的に表われたのが受難の場でした。
私たちがバッハのマタイ受難曲を聴くという行為は、遠藤が語るところのキリストの「X」に、弟子の立場で出会うという行為なのではないでしょうか。
なぜなら、私たちは毎日の生活において疑いもなく弟子グループたちのような駄目人間だからです。
受難に際して示した弟子グループの弱さと卑劣さ、裏切りと自己弁護はすべて私たち自身の姿でもあります。
そして、キリストの受難に出会うことによって彼らが大きく人生を変えたように、私たち自身もこの音楽を通して、今を生きることの問題を考えさせられるのです。
それだけに、気軽に聴ける音楽ではないというのが、偉そうな言い方ですが率直な感想です。
それにしても、この弟子グループというのは、マタイ受難曲のテキストを見るだけでも、立派とは言い難い存在です。師を売ったユダは言うまでもなく、他のメンバーも、ゲッセマネで必死に祈るイエスのそばでは眠りこけてはイエスに叱られたり、イエスが逮捕されると、今まで偉そうなことを言っていたのに、我先に全員が彼を見捨てて逃げ出してしまいます。
そして彼らの人間的な弱さが最も端的に現れたのが「ペテロの否認」でした。
ここには、人間にとっての最も恥ずべき行為、自分を信じ、愛してくれたものに対する「裏切り」が描かれています。
弟子達の裏切り
遠藤はいくつかの資料を基に、この場面の真実はペテロがイエスの身を案じて屋敷に忍び込んだのではなく、おそらく弟子グループを代表して交渉に赴いたのだろうと語っています。そして、すべての罪をイエスに押しつけ、自分たちもイエスを否定することで助命を嘆願したのだろうと語っています。
これはすさまじい裏切りです。
キリスト教神学の根本にある、人間の原罪を引き受けて十字架にかかったという抽象的なイメージは、ここでは生々しい現実だったのです。
まさに、イエスは彼らの罪を一人でかぶることによって、弟子グループは助かったのです。ペテロの深い嘆きはまさに弟子グループ全体の深い嘆きです。
しかし、彼らにとってつらいことは、その裏切りをイエスは許したという事実です。
人間というものは、裏切り行為に対して怒りの声を向けられれば、あれこれの理由をあげつらって自己弁護をすることができます。しかし、相手がそれを悲しげな目を持って許せば、自分の醜さがいやが上にも浮かび上がってきます。
自己弁護のきっかけもつかめなければ、自分という人間の駄目さ加減が身を引きちぎるように苦しめます。
これはなんというパラドックスでしょう。
ユダヤでは、十字架にかかった人はその死に際して、生きていたときの恨み辛みをぶちまけるのが習慣でした。弟子グループは、ペテロの交渉で生きながらえた後の恐怖は、死の間際に彼らの師であったイエスが何を語るかでした。自分を裏切った弟子グループに対してどれほどの怒りの言葉が語られるのか心底恐怖したはずです。
ペテロの否認から後の場面は、キリストの受難を影からじっと見つめる弟子グループの目で見るべきだと思います。
弟子グループの恐怖が頂点に達したのは、民衆が「バラバ」と叫んでイエスの死刑が確定した時点だったでしょう。やがて、十字架を背負ってゴルゴダの丘へ向かうイエスを見つめる彼らの心境はいかばかりだったでしょう。
いよいよ十字架に張り付けられたイエスがどのような怒りの言葉を自分たちに浴びせかけるのか、心底恐怖したはずです。
しかし、受難の成り行きは彼らの想像を絶したものとなりました。
イエスは、十字架上で怒りの言葉ではなく、裏切った弟子も、彼を侮辱し愚弄した民衆をも許したのです。
マタイのテキストには出てきませんが、「父よ、彼らを許したまえ。彼らは、その為すことを知らざればなり」は有名な言葉です。
そして,死に際しての有名な言葉「エリ、エリ、ラマ。サバクタニ」を聞いて、弟子グループの驚嘆は頂点に達します。
この言葉の意味は、遠藤の著作を通して初めて知ったのですが、死を前にしての絶望感の表れではありません。これは,詩編二十二編の冒頭の言葉であり、当時のユダヤ人なら、この冒頭に続いてどのような言葉が続くのかは誰もが知っていたはずなのです。
この詩編は、「主よ、主よ、なんぞ、我を見捨て給うや」と言う悲しみの訴えで始まっても、最後は、「我は汝のみ名を告げ、人々の中で汝をほめたたえん」という神への賛美に転調していくのです。
つまり、イエスは彼らを許しただけでなく、この屈辱の中でも最後まで神に対する信仰を失わなかったのです。それだけでなく、「父よ彼らを許したまえ」と裏切った弟子グループにも神の許しがあるように取りなしたのです。
「まことにこの人は神の子であった」
と言う叫びは、何よりも弟子グループの叫びととして聞くべき言葉だと思います。
しかしはじめにも述べたように、ここに深刻なパラドックスが発生します。
彼らは、「父よ許したまえ」というイエスの言葉をどのような気持ちで受け止めたでしょう。
死の間際の神への賛美をどのように聞いたのでしょう。
彼らは一切の自己弁護の手段を奪われて、自分たちの醜さと駄目さ加減が身を引きちぎる思いだったことでしょう。
遠藤はこのようなときに人間が取りうる路は二つしかないと語っています。
一つはそれでもなお、相手を徹底的に否定すること、もう一つは相手に許しを請うこと。
そして彼らはイエスに許しを請う路を選びました。
それがイエスの復活という概念に発展していく過程を遠藤は詳細に述べていますが、それはマタイ受難曲の範囲外の話です。
受難で示したイエスの姿は人間の理解を超えています。しかし、それを見つめる弟子たちの視点でなら、私たちはこの受難物語を自分の問題としてとらえることができます。
弟子たちは、それ以後も様々な紆余曲折を経ながらも、強い信仰の人として生涯を全うしていきます。
ごく普通の一般的な日本人にとって神という存在を突き詰めて考えると言うことは、そう滅多にあるものではありません。
しかし、この受難物語に向きあうとき、おそらくは弟子達の胸の中に存在したであろう、いつも悲しげな目をしたイエスの姿を浮かび上がらせることは可能です。彼らはそれ以後も、人間的な弱さをさらけ出しますが、しかし、最後の一線は崩すことなく信仰を守り続けました。
弟子達にとってのイエスの存在とは
おそらく、彼らは己の弱さをさらけ出す度に、彼らの胸にイエスの悲しげな目が浮かんだはずです。そして、その度にイエスは彼らを許し励まし続けました。
遠藤はそのように許し、励まし続けるイエスのことを「魂の同伴者」と呼びました。
そして、そのような「魂の同伴者」としてのイエスに、キリスト教信仰の根拠を求めるようになった経緯がこれに続くのですが、それもまたマタイ受難曲の範囲外の話です。
マタイ受難曲のなかで、そのような「魂の同伴者」としての神のイメージが最も鮮明に現れるのが、「ペテロの否認」の場面です。
この最も忌むべき裏切りに対しても、その裏切った心の痛みは私が最もよく知っていると言わんばかりに許しを与えます。その時、彼が予言したように鶏は暁を告げるのです。
かつて、吉田秀和氏は、リヒターの演奏でこの場面を聞いて涙がこぼれない人は音楽を聴く資格がないと発言していました。この大仰な物言いもマタイについてだけは許されるような気がします。
バッハの筆も、この場面ではもてる技術のすべてをつぎ込んでペテロの深い嘆きを歌い上げています。
聖書には人間のドラマのすべてが詰まっていると言われます。その中でも、受難の場面での人間ドラマには実に多くのことを現在の私たちにも語りかけます。
ですから、マタイ受難曲を演奏するという行為は、そのような重みを全身で受け止めて、己の生き方を問いかける営みと常に等価です。そして、メンゲルベルクのマタイは大戦前という異常な社会状況下における「生きる」と言うことの意味を問いかけた演奏であり、そう言う演奏であったが故に時代の証言者となり得たのです。
しかし、欲を言えば、その演奏はある特殊な社会状況に縛り付けられてるが故に普遍性は希薄です。
その意味で、このドラマの重みをしっかりと受け止めて、その重みを普遍性を持って表出している演奏は、リヒターの58年盤しかないように思います。
これは勝手な思いこみかも知れませんが、遠藤の著作を通して受難物語の詳細を知るにつれて、その思いはいっそう深くなります。
バッハ:マタイ受難曲
そして、90年代以降ヨーロッパを覆い尽くしたピリオド演奏というムーブメントが、この「重み」を受け止めることができなかったことだけは否定しようのない事実です。
私のピリオド演奏に対する強い拒否感の原点はここにあります。